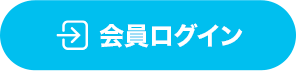『Hyuga Pro presented by Asahi Softdrinks』終了!
2008-10-12 更新

プロジュニア『Ocean & Earth Teen Age Rampage』も同時進行で行なわれ、12日に全ての勝利者が決定しました。
期間中はウネリに恵まれ、ファイナルデイもムネ~頭のサイズをキープ。次第に風の影響が気になりましたが、アクションしやすい掘れた波が多く、コンテストには十分なコンディションでスケジュールが進行しました。
まず、WQSですが、奈良県出身で現在は宮崎に拠点を置いている北田力也が逆転劇を繰り返し、注目を集めます。ラウンドオブ16では東川泰明、田嶋鉄兵を抑え、辻裕次郎と共にラウンドアップ!マンオンマンとなったクウォーターファイナルでは9月に福島北泉Pで行なわれた『MURASAKI PRO KITAIZUM』を制した田中英義に対してコンビネーションスコアの圧勝。続くセミファイナルでは中村昭太に敗れましたが、ここまで勝ち抜いてきたのは大健闘と言えるでしょう。
ファイナルは北田力也を抑えた中村昭太(写真)&セミファイナルでダレン・ターナーを僅差で敗ったジェイソン・シバタの対決。
序盤からダッシュをかけたのは中村昭太。「来るもの拒まず」といった感じで、とにかく波に乗りまくり、5pt台と6ptをまとめて主導権を握ります。一方、ジェイソン・シバタはアウトでじっくりと波を待つ作戦。ファーストウェーブで5pt台をスコアした後はポイントが延びませんでしたが、ラスト数分で形が良いライトのセットを掴み、ビッグターンを繰り返して7.00で逆転!しかし、中村昭太の勢いは止まらず、すぐに6.75を返して再逆転に成功!ジェイソン・シバタが再度逆転に必要なスコアは5.75と時間さえあれば返せない数字ではありませんでしたが、時すでに遅し...。中村昭太が接戦を制して優勝を決めました!
続いて行なわれたLQSのファイナリストは、JPSAのカレントリーダー、ケコア・ウエムラと、スタイリッシュなライディングを武器に勝ち上がってきたショーロクこと宮内謙至。ロングにしてはハード気味の難しい波にショーロクは手こずりますが、ハワイアンのケコアにはお手の物。ヒート中盤に9.25と8.00を続けてメイクし、ショーロクをコンビネーションスコアに追い込みます。ショーロクは後半に追い上げをかけますが、6pt台を二つスコアするのが精一杯。完璧な形でショーロクを抑えたケコアが勝利!
プロジュニア『Ocean & Earth Teen Age Rampage』
21歳以下のクラスは、WQSで優勝した中村昭太がダブルエントリーでファイナルに進出。積極的にエアーを取り入れたサーフィンで9.00を叩き出しますが、バックアップスコアが足りず。このクラスで常に上位に顔を出す大澤伸幸もパワフルなターンを刻んでアピールしますが、6pt台以上が出せず、爆発力に欠けます。そこにチャージをかけたのが千葉・銚子の黒澤賢一。派手な技こそ無いものの、確実にポイントを重ね、後半の主導権を握りながら最後までリードをキープ。ジュニアとは思えないハイレベルなデットヒートを制し、ビッグイベントでの初優勝!
16歳以下で争われるカデットでは、7pt台を二つまとめた加藤嵐が優勢の展開。他の選手に比べて安定感もあり、『MURASAKI PRO KITAIZUM』に続く2連勝も目前でしたが、終了間際に新井洋人が目が覚めるようなビッグターンを披露し、9.50ptをメイクして3位から1位へ一気にジャンプアップ!加藤嵐はすぐに8ptを返しますが、逆転にはスコアが足りず、新井洋人が今シーズン初の勝利を収めました。
海から上がると普通の少年のように感じられるカデットの選手達ですが、サーフィンしている姿は大人顔負け。そのレベルは年々確実に上昇しています。この世代の選手達が良い形で成長してくれれば、日本人初のASPワールドツアー入りというニュースも遠い話ではないのかも知れません。
今回のイベントではヒート中に多数のメッセージが送られ、MCのニック・ミタと伊久良ジョージも忙しく読み上げていました。各選手の地元からの応援の声や、LQSではハワイからケコアを応援するボンガのメッセージも届いたほど!インターネットの普及により、ライブ中継が当たり前のように行なわれ、遠い場所からもメッセージがダイレクトに届く環境は素晴らしいと思います。
会場に直接足を運んで応援するのが理想ですが、ここまでライブ中継が進化している今、新しいサーフィンコンテストの観戦方法が確立されていると言っても過言では無いのでしょう。
photo: ASP Covered Images